クナを聞く 第127回
ブルックナー編その6-4 ブルックナー:交響曲第9番
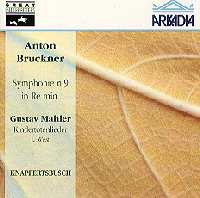 |
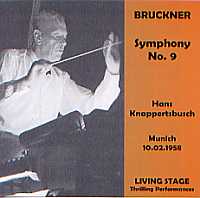 |
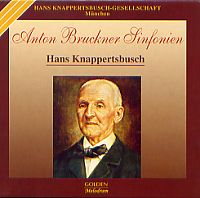 |
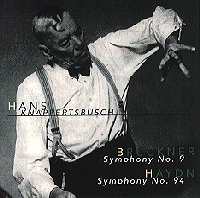 |
 |
(rec.1958/2/10 L)
Arkadia/CDGI 710.1(Italy)
Living Stage/LS 1009(Italy)...Refarence
Golden Melodram/GM 4.0008(Italy)7CDs
Music & Arts/CD-896(USA)
Orfeo D'or/C 578 021 B(Germany)
- Arkadia/CDGI 710.1(Italy)
Hunt盤の時代からあるから、1958年のブルックナー:交響曲第9番のCDとしては最も古いか。小生はHunt盤を持っていないが、ほぼ同じ音だと思われる。帯域は狭く、少しこもり気味の音ながら聞きにくい音ではない。若干リヴァーヴを加え、ステレオプレゼンスがあり、緩やかに音が左右に拡がる。 - Living Stage/LS 1009(Italy)
Arkadia盤に比べると帯域がかなり拡がり、リアリティある音になっている。ただ、原テープの劣化が感じられ、たまに音が抜けたりする。緩いワウが感じられ、強奏でほんの少しだが混濁する。 - Golden Melodram/GM 4.0008(Italy)7CDs
Arkadia盤やLiving Stage盤に比べると、出だしは落ち着いて聞こえるものの、帯域がかなり狭く聞いていてフラストレーションが起きそうな音。高域の音が全て丸くなっており、Living Stage盤の方がリアリティがあった。強奏でかなり混濁する。 - Music & Arts/CD-896(USA)
第1楽章出だしの音のたたずまいは「お!」と思わせるが、帯域は狭く情けない音。高域に伸びがなく、ステレオプレゼンスが加えられ、聞き難さはないがあまりいいとは言えない。 - Orfeo D'or/C 578 021 B(Germany)
バイエルン放送局のテープをトン・アイヒンガー、オトゥマール・アイヒンガー、ゴットフリート・クラウスがデジタル・リマスタリングした。綺麗な音だが、低域が乏しくライヴ録音のリアリティには欠ける。音圧レヴェルも低く、整音のし過ぎか。音の混濁がなかったり、欠落がないのはありがたいが、再生側でかなり加工してやらないと、例えばLiving Stage盤のリアリティには届かない。
・・・と諦めてStaxのイヤスピーカーでモニターを始めたのだが、Orfeo D'or盤を聞いていていらつき始めてしまった。どこか音に力がないのだ。綺麗な音なのだが、芯のない、その脱力するような音の作り方に途中でイヤになってしまい、仕方なくLiving Stage盤を聞き直す羽目に陥った。普通の方にはOrfeo D'or盤をお奨めする。Living Stage盤はかなりやくざな音だ。
ただ、装置を変えるとOrfeo D'or盤も多少は聞きやすくなる。Sennheiser/HD-580という低域がかなり出るものの、大ざっぱな音のするヘッドフォンでは、それほど違和感がなくなる。アンプのボリュームの位置を1dBか2dB上げ、トーンコントロールをいじり、なんとか聞けるレヴェルにはなった。
しかし、迫力を綺麗にぬぐい去ってしまったOrfeo D'or盤に、小生は納得することができなかった。シンセサイザー風に言うと、音のエンヴェロープはアタック、ディケイ、サステイン、リリースから成立していて、ハープやハンドベル以外の普通の楽音にはリリース(持続)はない。弦楽器などでカスケード効果を得るためなら話はまた別だが、音はほぼアタック、ディケイ、サステインでできあがっている。ライヴ録音の場合、サステインの長く伸びる音が残響とともに聞き取れるのだが、Orfeo D'or盤では、ノイズ成分と一緒にそのサステインがカットされ、極めて速く減衰する。そのため、ちゃんと続いているはずの音のリアリティがなくなってしまっているのだ。スピーカーでモニターするのならまだ我慢ができるが、イヤスピーカーやヘッドフォンでは聞いていると、あるべきはずの音がなくなってしまっているので、ストレスが溜まってしまう。
結局、音に欠落があったり、ホワイトノイズが盛大に被っていたり、音揺れがあったり、強奏での混濁はあっても、Living Stage盤という、あまり信の置けないレーベルのCDをリファレンスにせざるを得なかった。情けないといえば情けないが。
第1楽章
初めてこの演奏を聞いたとき、とんでもない珍演に聞こえた。オーケストラは荒っぽくて金管はたまにはずすし、クナのテンポ変化は恣意的で、朝比奈隆やマタチッチ(チェコ・フィル盤、ウィーン交響楽団盤)の演奏録音を聞き慣れている耳には、とてつもなく変に聞こえる演奏だった。
クナバカになって、さまざまなクナの演奏に接していると、クナはミュンヘンの聴衆を前に演奏するとき、とてつもないサービスをしているのではないかと思えるようになったが、今聞いても「ここまでやるか?」という部分の多い演奏記録である。
聴衆のざわめきが収まらないうちに演奏が始まる。音楽はゆったりと進んで行き、金管の盛り上がる21小節でホルンが情けない音を出してしまう。それで演奏が崩壊してしまうことはないが、波乱を含んだ出だしである。27小節からの第1ヴァイオリンは、ベルリン・フィルほどの没入度や巧さは感じないが、まずまずしっかりと感情移入をしている。練習番号Bでの、雨音が垂れ、それが段々繁くなって行くような木管楽器と弦楽器のピツィカートは、Living Stage盤ではダンゴ気味だ。
音楽が段々と盛り上がり、練習番号Cに入る前の61小節で、管弦楽はかなりずれている。クナは溜を作りたかったようで、弦楽器はリタルダンドしようとしているのに、トランペットがそのままの速度で突っ込んでしまう。弦楽器も慌てて減速をやめ、つじつまを合わせているように聞こえるのが面白い。練習番号Cは面白いほど盛り上がり、白熱の頂点を築く。
77小節から、弦楽器群のピツィカートに、ブルックナー特有のふざけているのか真面目なのか分からない、自然音の模倣のような短い木管楽器のつぶやきが聞こえる。
練習番号Dから、シミジミとした弦楽器によるメロディが始まる。1958年盤でも、クナのテンポは速めだ。
練習番号Eで、青空にとけ込んでゆくような清々しい音楽が奏でられるが、125小節あたりでLiving Stage盤は原テープの劣化のためか、情けなく音抜けがあったりする。126小節の後半、チェロ・パートでもの凄いアッチェランドがかかる。127,128小節では全ての弦楽器が合っているようには聞こえないが、129小節で大きくリタルダンドし、131小節から元のテンポに戻る。フルトヴェングラーでもやらないぜ、と思えるテンポの揺らせ方で、小生初めてこの部分を聞いて、クナの演奏には思えなかったことを思い出す。まるで、田舎芝居の大根役者が見得を切っているようだ。オーケストラの精度が良かったら、恐らくかなり決まっているように聞こえるだろうが、残念ながら決めは今ひとつだ。それでも、130小節最後の引き伸ばされたチェロの音はチャーミングだ。
131小節からの音楽は、クナはそこに生命を吹き込むかのように、極めて魅力的な表情を引き出している。141小節から142小節でトランペットが突出気味だが、弦楽器の響きは美しく、147小節からはうっとりとするほどで、152小節のリタルダンドは夢見るようで美しい。さらに153小節からの木管楽器とホルンは寂寥感をたたえている。
練習番号Fは、どこかモッタリと始まる。Living Stage盤はところどころ音がかすれて抜けてしまうのは残念だが、クナとバイエルン州立管弦楽団は実にローカルな味わいを奏でてゆく。ということは洗練された響きではないと言うことだが・・・(^^;。179小節からは、まるでフランスのオーケストラを聞いているように、各楽器が自己主張をしているように溶け合わず、バラバラだ。それでも、219小節からはひじょうに美しい音楽を聞くことができる。
練習番号Jで音楽は静かになり、その静けさの中から徐々に盛り上がって練習番号Cのファンファーレが繰り返される。268小節からも、もう1回繰り返されるが、トランペットの音に抑制が効いておらず、華々しいが弦楽器の表情とは少し齟齬を起こしているようだ。
練習番号Fからの、弦楽器の思いピツィカートの上を、木管楽器がメロディを奏でてゆく箇所もテンポは速めだ。音楽は緩やかな稜線を描くようにゆったりと低い丘を築くようにテンポが少し速くなるが、ここではクライマックスは訪れない。ノーヴァク版にはない302小節の木管楽器による経過句を経て、ブルックナーの美しく良き思い出を描くような魅力的なメロディがしっかりと演奏されてゆく。その美しい追憶に不安が宿るような、あるいは別の期待感が高まるような321小節から、原典版信者が見たら卒倒するようなスコアの改編があるが(まだ可愛い方か)、クナはテンポをかなり速めに取り、駆け抜けるように練習番号Nの巨大なクライマックスになだれ込んでゆく。なんという、田舎臭い演奏なんだろう(^^;;;;。
練習番号Nに入ってからも、336小節の後半で管楽器の3連符に併せてレーヴェ初版ではティンパニーにも3連符で叩かせる。1950年のベルリン・フィルとの演奏記録では自然に聞こえてしまった部分が、まるで拡大されて聞こえる。嵐の中をコラールが吹きすさぶようなクライマックスが延々と続き、練習番号Oのしっかりとした足取りが明るい表情を伴うような、勝利への驀進のような音楽にその表情が変わってゆく。まるで行進曲のような明るい表情だ。練習番号Pに入る直前、366小節後半の3連符はリタルダンドがかかり、芝居気たっぷりの経過句が聞ける。
練習番号PからQにかけて、かなり明るい華々しい音楽が聞けるが、380小節後半の3連符に入る直前、クナの足音一発が聞こえ、音楽は更に登り始める。音楽は高みに昇りつつも、395小節で奈落に落ちるように転落し、静かだが不気味な音楽へと、その表情を変える。その不気味ティンパニーのロールの中から、400小節からの哀切きわまりないメロディが第1ヴァイオリンで奏でられ、ヴィオラがその悲哀の感情を増加させ、第2ヴァイオリンやチェロが寂しさを更に引きだしてゆく。ブルックナーの素の感情がそのままにじみ出てくるような部分だが、クナはさすがにこの部分ではもの凄い寂寥感を音にしてゆく。その寂寥感がゆったりとリタルダンドし、すすり泣きの中に音楽は止まってしまうのではないかと思えるような凄惨な音楽が聞ける。
練習番号Sから、その寂寥感を慰撫し、立ち直ってゆくかのようだが、クナはテンポを速めに取り、心の平安と信仰を取り戻してゆくような音楽を聞かせる。練習番号Tに入るまで、少しそそくさしたテンポだが、音楽の表現したいものが理解できると、実に感動的な音楽をクナは形作っていることが分かる。その素っ気ないテンポから、ブルックナーのいじらしいほどの心情がこぼれ出てくるかのようだ。450小節からのアッチェランドは、その切実な心情を豊かに肉付けしてゆく。そのため、455小節からのリタルダンドが実に美しく、豊かに美しく聞こえる。少しやりすぎのようにも聞こえるが・・・(^^;;;;。
練習番号Uから、悲哀も信仰への希求も飲み下し、どこかうら寂しいながらも決意に充ちた表情の音楽に変わる。471小節からその表情が劇的と言えるほど明るさを増し、ほんの少しの浮沈はあるものの、練習番号Vからは影を含みつつも心に平安を宿したかのような進行を見せる。音楽はどんどんと登り詰め、501小節の勝利へとたどり着く、503小節、504小節のホルンがその勝利を静かに祝福し、507小節、508小節のレーヴェ初版の楽器の変更は大きな感動をもたらす(前回のログで、ノーヴァク版にはない小節の追加と勘違いしたのだが、楽器の変更だった)。509小節から、その勝利への賛歌のようなコラールが奏でられ、第1楽章はフィナーレに向かう。音楽は信仰の勝利と天国の眩いばかりの色彩を奏で、第1楽章は終結する。オーケストラはちょっと頼りないか(^^;。
第2楽章
クナの演奏を聞き慣れてしまうと、練習番号Aに入るまでのオーケストレーションはレーヴェ初版の方が面白い。ブルックナーが本当に欲していたかどうかは別にして、フルートとファゴットが活躍するスケルツォの開始はなかなか魅力的だ。
クナはかなりキビキビとスケルツォを演奏させてゆく。練習番号Aからの破壊的な音楽も、単に暴力的なだけではなく、ブルックナーの哄笑だということが分かる。練習番号Bからの、全ての事象に風のように意識を忍び込ませて歓びを得る、というのはブルックナーのスケルツォの常套だが、スケルツォ全体を貫く破壊的でいて実は悦ばしい(ちょっと病的か)ブルックナーの感情をしっかりと描いてゆく。Living Stage盤は音の抜けが激しく残念だが、だれかアイヒンガー&クラウスと同じテープを使って、もっとましなリマスタリングをしてくれないものかと思えてしまう。
練習番号Eから、ブルックナーの優しさとユーモアが音になって行く。クナの描き方は直截的で、ブルックナーのいじらしいほどの歓びにあふれたフレーズを何のてらいもなく演奏させてゆく。実に美しい音楽が奏でられてゆく。
練習番号Gで練習番号Aの破壊的な哄笑に戻るが、クナは足音一発でオーケストラの響きを引き締める。金管の響きを全開にして、聴衆にその管弦楽の快感を味あわせる。
トリオにはいる前、レーヴェ初版ではティンパニーが居残ったようにスケルツォのリズムを刻み、トリオへの橋渡しをするがこれは少しやりすぎのような気もする。
トリオに入ってからも、練習番号Bまではスケルツォの気分を少し引き継いでいる。それが、練習番号Bから夢見るような表情に変わるが、クナのメロディの奏でさせ方が生きているような部分だ。ドビュッシー:「牧神の午後への前奏曲」のような、優しく明るい幻想が活き活きと演奏される。練習番号Cに入る前のリタルダンドが実に美しい。
練習番号Cから、練習番号Bが音を変えて演奏される。まるでブルックナーの子守歌のように夢を見るようでいじらしい音楽を聞くことができる。夢を見るような部分はもう一度繰り返され、スケルツォに戻る。
クナのテンポはかなり速い。その悦ばしい感情が時に荒々しく、時に優しく、サービス精神豊かに演奏されてゆく。誰かが何かを落とす音が聞こえたりするが、スケルツォは間然とすることなく終結する。
第3楽章
かなり豊かな音で、ブルックナーの惜別のメロディが聞こえる。もの悲しく、そして幾分明るいという矛盾した感情を秘めながら、練習番号Aの波のような明るい感情の爆発が聞ける。クナの1958年の練習番号Aはかなり速い。そして、練習番号Bからの「生からの別れ」も、少し速めのテンポで、あまりその悲哀に拘泥したくないかのように進行する。
しかし、練習番号Cから極めて美しい表現が聞ける。幾分瞳孔が開き気味ながら、慈しみと明るい悲哀を伴いながら魅力的な音楽が進行する。練習番号Dの美しさは変に持って回った演奏ではないだけに、実に素晴らしい。
練習番号Eから再びアダージョ冒頭に戻るが、1950年のふたつの演奏記録ではあまり感じなかったが、1958年盤ではまるでワーグナーの演奏のように響きが豊かで、その感情の襞は美しい。89小節から91小節の美しさは尋常ではない。練習番号F二はいる直前、92小節の低弦域の息の長いリタルダンドは凄みがある。
練習番号Fから、決然とした響きの音楽の変わる。冒頭、金管楽器が遅れ気味で、その後トランペットが喧しいほどだが、録音のバランスが悪かったのか。
音楽は静かになり、練習番号Gから低弦域がオルガンのペダルでコラール旋律を弾いているような中、第1ヴァイオリンが優しげなメロディを奏でる。クナのうねるような低弦域の弾かせ方は健在で、別々のドラマが融合してゆくような優れた演奏を聞くことができる。そのドラマが高調し、練習番号Hから、練習番号Aのこだまのような波が繰り返される。ホルンが少し不調だ。
練習番号Hから、まったく別の感情が支配するような本当の意味での第3楽章のクライマックスが訪れる。その音楽は優しく慈愛に充ちて平和だ。
練習番号Kは音の圧迫感の強い強烈な音楽だが、後半優しくなり、練習番号Lの神秘的な音楽が奏でられる。ここも、練習番号Hとは別の意味でクライマックスだろう。クナならではの幻視するような美しい瞬間が訪れる。
音楽は盛り上がってゆくが、アンチクライマックスのように静かになり、練習番号Mのヴィオラが分散和音を奏でる中、ヴァイオリンと木管が豊かなメロディを奏でるのだが、クナのテンポはかなり速めだ。練習番号Oから低弦域の下降音型が加わり、音楽は壮大さを増して行く。練習番号Qの強烈なフォルテシモの響きが持続し、より巨大なクライマックスを築くのかと思わせながら、206小節でいきなり終結する。練習番号Rの最初の猫だましのような音で、壮大な夢を裁ち切り、別な夢へと聞き手を誘って行く。練習番号Sで、音楽は盛り上がろうとするが、218小節でその感情を押し殺すようにリタルダンドし、静かな練習番号Wの音楽から、練習番号Xの慰めと平安に充ちた音楽を奏で、第3楽章は平穏に終結する。
クナのブルックナー:交響曲第9番としては、まずベルリン・フィルとの1950年1月28日のドレス・リハーサルの録音を聞くべきだ。そこには、クナのブルックナー:交響曲第9番で表現したかった音楽が詰まっている。30日のライヴはオーケストラが暴走気味で、特に第1楽章など必ずしもクナの音楽ばかりにはなっていない部分がある。
1958年盤は、今だ満足できる音でリリースされておらず、Living Stage盤を聞いても、Orfeo D'or盤を聞いてもフラストレーションを起こすだろう。それに、クナはミュンヘンの聴衆を前にしたときの気安さというか、気前の良さというか、クナのサービス精神が全面に出た演奏で、かなりローカルな味わいになっている。トランペットの音も突出気味で喧しいほどだが、第2楽章、第3楽章の意味深さはクナならではだ。
クナの他にさまざまな指揮者のブルックナー:交響曲第9番を聞いてみた。残念ながら、クナと同じレーヴェ初版で演奏しているものはなかった。アドラーの演奏が昔、LPで出たことがあるようだが、残念ながら現在は聞くことができない。毎日毎日、うんざりするほどブルックナー:交響曲第9番を聞いたが、その中で、Ode Classicsからリリースされた2種類の録音のうち、ヘルベルト・ケーゲル指揮ライプツィヒ放送交響楽団の1969年4月1日の演奏の素晴らしさに驚いてしまった。雑音があり、オーケストラのミスもあるが、数あるブルックナー:交響曲第9番の録音の中では、最も小生の耳をそばだたせてくれた演奏録音だった。
その他では、カラヤンの2種の録音(DG)、フルトヴェングラーの1種だけ残されている録音(DG)が小生には実に面白く、ヴァントの4種類ある正規録音(RVC)も良かったし、レーグナーのテンポの速い演奏録音(Berlin Classics)もなかなか素晴らしかった。
次回、「クナを聞く」はヨハン・シュトラウスⅡ世の音楽を取りあげる。